
| ホーム | |
| Webで読む 武道通信 |
|
| Web武通 | |
| 購入案内 | |
| 新刊案内 | |
| 既刊案内 | |
| 兵頭二十八 を読む |
|
| オンライン 読本 |
|
| 告知板 | |
| リンクHP | |
| 無銘刀 (掲示板) |
|
| Web 論客対談 |
|
| 茶店の一服 | |
| ひとこと 聞きたい |
|

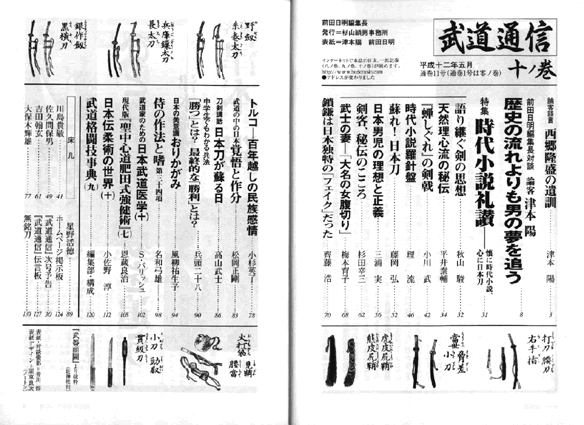
今巻は「前田日明刀」を紹介。
本人が選ぶというのも照れるということから、編集部が選ぶ、ということに。
昨年度、新作刀剣展で特賞に輝いた現代刀の名作の一品。
論客 津本 陽
歴史の流れよりも 一人の男の夢を追う
| ほんのさわりですが。 津本 いつだったかの直木賞の授賞式に、もう退社なさったんですが, 豊田さんが顔を見せまして、この間探しものをしていたら、川口松太郎さんから、「津本陽に剣豪小説書かせろ」という葉書が出てきたといって見せてくれました。 前田 そうなんですか。自分たちが今、津本陽の剣豪、歴史ものを読めるのは川口松太郎のお陰だったんですか。 津本 それまでマゲモノとかはやる気なかったんです。でも、人からやってみろと言われると、珍しいというか、好奇心が湧くんですね、やったことないから。それでやったんです。そうしたらこれが面白いんですわ。 津本 いよいよ豚を斬ることになり、ま ず先生がボンと斬ったら直径10・の骨が出てきたんです。もう一つは3・くらい。「骨が太いのと細いのと二本あるし、死んでからかなり日がたっているから硬いぞ」と先生が言った。 さっきと同じように、大きく振りかぶって振りおろすと今度も手ごたえゼロ。音もなく斬れていた。ただまな板をパーンと叩いただけですわ。太腿は二つになり断片が見えました。斬ったというより、いつの間にか斬れている、そんな感じでした。 前田 本来、日本刀というのは怖ろしいほどよく斬れるですよね。スポーツ・チャンバラ会長の田辺哲人さん、居合をやっていまして、昔、伺った折、斬れる刀と斬れない刀とこんなに違うんだよというんで実験して見せてくれました。巻藁を土台の上に置いて、刀をその上からストンと落とすだけなんです。よく斬れる刀は落としただけでスーと半分くらい入って斬れない刀はポンと弾かれる。。 津本 塚原ト伝、伊東一刀斉、宮本武蔵とかいう一流の剣豪、あれはやはり合気ですよ。 前田 剣も合気ですか。 津本 ええ、剣も合気だと思いますね。柳生新陰流宗家の柳生延春先生は竹刀持って出てきた相手をパッと見て、腕がわかるといいますからね。これが合気ですよ。千葉周作とかあんなに試合しても負けたことないでしょう。あれは合気です。私らにそんなこと言われても、何のことかさっぱりわからんですけど、かつての剣の達人たちはわかっていたんだと思います。 特集 時代小説礼讃 懐に時代小説、心に日本刀 日本近代文学が切り捨てた、剣の心を語りついできたのが時代小説であった。 日本の文化は、歌の世界と武の世界の緊張しあった調和であり、武の象徴は剣であった。 日本人の得物(えもの)である時代小説を懐に、そして心に日本刀を差せA日本人よ。 特集目次 語り継ぐ「剣の思想」 秋山 駿 天然理心流の秘伝 平井泰輔 『蝉しぐれ』の剣戟 小川 武 時代小説羅針盤 理流 蘇えれ!日本刀 藤岡 弘 日本男児の理想と正義 三浦 実 剣客、秘伝のこころ 杉田幸三 武士の妻―「女腹切り」 梅本育子 巻頭宣言! 語り継ぐ「剣の思想」 秋山 駿 文芸評論家 さわり:日本民族にとって武の文化の象徴である剣。 日本刀を語ってきた時代小説はなくてはならぬものでる。 日本の文化の特性は二つの中心が緊張し合った関係で調和していることだ。一つは古近和歌集から始まる歌の世界、 もう一つはもののふの剣の精神、武の世界。 万葉集まではこの二つが合体していたが、古今和歌集から分かれた。しかし武の文化と歌の文化は共に磨きあっている。日本人の礼儀作法の源は弓馬の誉れ高い武門の小笠原家の作法であり、剣の極意は大方、歌に読まれる。 日本民族にとって武の文化の象徴である剣、日本刀を語ってきた時代小説はなくてはならぬものでる。 |

| さわり:新撰組、天然理心流の通説を覆す。初代近藤内蔵助はお庭番だった。 近藤勇、土方歳三は徳川を護るべく宿命を伝授されていたのだった。 江戸開幕時、家康が江戸城の西の防備して甲州の武田の遺臣団を八王子とその近郊の村に土着させた。それはここが江戸の水源地であり、東海街道と甲州街道の出合う場所であったからだ。その目的で組織された「八王子千人同心」の多くが、当時天然理心流に入門していた。千人同心と一身同体といえる天然理心流が反幕府の勢力鎮圧の浪士組から無視されるというのもおかしい。 それなのに天然理心流が、無名の一流派としか後世には知らされていない、何か不可解である。 江戸に本道場があり、武士の門人の中に傑出した者もいたのに、跡目は皆、地元の農民である。天然理心流は流派の名を上げるなど一見もなく、常にその土地に根付く事を目的にしていたことは明白である。それはなぜか? これが私の”ある疑問”であった。 |
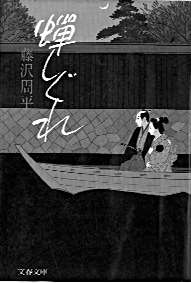
| さわり:名作『蝉しぐれ』の三場面の剣戟の是非を問う。果たして文四郎は勝ったのか。 藤沢周平氏の『蝉しぐれ』は時代小説の名作と評判の高い作品である。そしてこの作中にある、幾つかに剣戟シーンも読者を堪能させるものであると聞く。藤沢氏は剣道、剣術とは無縁な方ではなかろうかと想像する。そこがまた小説の小説たるゆえんであり、決して異を唱えるものではない。 『蝉しぐれ』は、主人公牧文四郎の青年期の成長が描かれ、その節目、節目に他道場との竹刀試合、藩政にからんでの争い、また町角で刺客に襲われる剣戟シーンが描かれている。 |
時代小説 SHOW http://www.jidai-show.com/
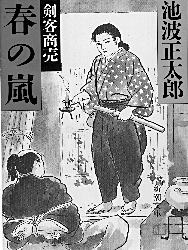
| さわり:「サラリーマンの通勤時間の癒し、愉しみ」の先入観は崩れた。 時代小説はいまや世代、男女の枠を超え、愉しまれている。 歴史小説は史実を踏まえ、作者の想像力を駆使して、事件の背景分析や人間ドラマを加えて、歴史上の事件や人物を描く。歴史小説は時代小説の代表的なジャンルの一つと見なすことができる。司馬遼太郎、池波正太郎、柴田錬三郎、藤沢周平、隆慶一郎…。時代小説の巨星たちは逝った。しかし、かれらの遺した名作は、色あせないでいまも輝きつづけている。ページをめくれば感動の海に浸れる。その薫陶を受けた作家たちが活躍し、新しい時代小説が日々生まれている。いま、時代小説が面白い。 |
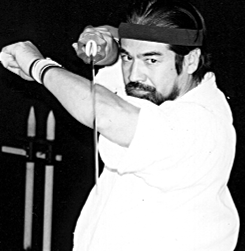
| さわり:少年時代に観た時代劇映画が、いまの私の夢を育む。 田舎の少年の唯一の娯楽は時代劇映画だった。当時、早朝割引の三本立で一日中時代劇映画を観ていた。学校から帰ると一目散に映画館へ行ったり、学校をさぼり映画館で弁当を食べたこともあった。 子供ながらにも彼らに足が地に着いた存在感を感じていた。そして死を恐れることなく、恥を受けることを許さず、エゴを制する力を持っていた。さむらいの魂であり、武道の精神性のシンボルである日本刀を通して、日本と外国がいままでと違った関係が作れると、そのとき予感した。 まだまだ、特集つづきます。お楽しみに。 |
読みごたえ十分。読力でかみ砕いてください。
古今東西の武器の起源から鎖鎌の発祥をたどり、この謎に挑む。
アジアの民族が情を通して作り出そうとした、もう一つの歴史物語
トルコ――百年越しの民族感情
新聞は金の力と伝えた。が、トルコ人なら誰もが知る
日本とトルコとの一世紀前の出来事があった。
覚悟と作分
遊芸に覚悟と作分があるように武芸にも覚悟と作分があった。
低くなってもなお美しい人がおりかがみのできる人なのだ。
■
待っている……。この無限で永久的な闘争の世界を、どう生き抜くのが
いちばん利口だろうか? 人々は、大昔からそれを考えていた。
現代の剣道家たちよ、日本刀を取り戻そう。
まちがいだらけの整体認識
肥田式天真療法
恩蔵良治編
柔術の技法(三)締め技と固め技
■
佐久間保男(白鞘師) ライフルと白鞘
吉田翰玄(奉公人HAL) 坂の向こうにつづく道
大保木不全(大学教員) 「武」の素描
星野活徳(ロンドン・ジャパンブック店) 英国武道家の嘆き
武の原義を曲げてきた我らはいま、
己に合った得物を選び、戈とし、
二度目の敗戦を防ぐべく趾を進めよう。
| 司馬遼太郎が自著で一番好きな作品は何か、と問われたとき、しばし目を宙に漂わせてから『燃えよ剣』と答えたと、どこかで読んだ。しばし目を宙に漂わせたというところが玄妙である。が、単純な輩は「そうか司馬遼もやはり新撰組か、土方歳三か」と悦に入った。輩は近藤勇らの道場、試衛館があった市ヶ谷甲良町を彷徨(うろつ)いたり、我が街から駅、二つ目の日野にある土方歳三の墓に参ったりしたことがあった。 土方らの天然理心流の祖は、徳川幕府を護る任をもっていたとの説が今巻にある。その是非は読者諸氏に大いに愉しんでいただくとし、やはり時代小説は、いまから遠い昔を振り返った小説(ロマン)であるゆえ、現代人の歴史認識、生活、身体感覚の重力の中にある。封建時代の身分差の認識、剣先が頬をかすめる恐怖、漆喰の闇も想像するしかない。いかに登場人物の生き方が琴線に触れようとも、その人間の行動原理を完全に解き明かすものではない。 「武」は「戈を止」と解釈したのは中国の儒家で、それも一儒家の認識であり、原義は「趾で進む」と知り、溜飲を下げたと、今巻「床几」で大保木さんは言う。”徳川武士道”が、この解釈を奨励したのは想像に易いし、先の敗戦後、多くの武道家は平和憲法の下、この解釈にすり寄った。 五稜郭、函館の地で土方歳三は馬上にまたがり一人、白刃を掲げ砲隊に突き進んだ。この立居振舞いは「武」の結晶のきらめきを後世に残してくれた。蛇足だが敗戦国で生まれた少年の輩が、降伏の屈辱を多少なり救われたのは「神風特攻隊」であった。 もし日本が第二の敗戦を喫すとわかったとき、我々は末裔に「武」の欠片でも残せるだろうか。欠片のつもりの『武道通信』も十人の論客が出揃った。地平に黒々とした影を投げかけ、己の得物で一人戦っている志士たちである。次巻、もう一人加え、十一人の論客が一同に会する。(杉山頴男) |